 |
 |
 |
 |
 |
 |
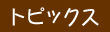 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
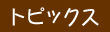 |
|
9月例会予定 相島島内一周 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
相島(あいのしま、新宮町のHPではそのように表記されています。なお「あいしま」という島は山口県萩沖にあります)は新宮町沖の玄界灘に浮かぶ小さな島です。 平成19年に例会を計画しましたが、台風の影響で流れてしまいました。 まだ暑さも残る9月、今月は山を離れてウォーキングを楽しみます。島内1周、約5.4km、多少のアップダウンもありますよ。適宜休憩をはさみながら、気持ちのいい 汗を流しましょう。 この島は5〜7世紀の古墳(積石塚)、元寇での戦死者の供養塔、秀吉の朝鮮出兵時の遺跡、江戸時代の 朝鮮李王朝の通信使を接待した客館など、各時代の遺跡などが残っています。しばし、歴史のロマンにもひたってみてはいかがでしょう。また、日頃はあまり見ることの ない、海の風景を楽しみながらの散策ともいえます。おだやかな海にはミキモト真珠が行っている真珠の養殖場が広がっています。昼食の弁当には、アコヤ貝の貝柱の 刺身がついているかも。 ただ残念なことに、8年前に下見で訪れたときよりも、一部のスポットは雑草が生い茂り、荒れているように感じました。また日蒙供養塔は、寄りつきの浜辺の道が丸い 小石ばかりが転がる道で、下手をすると足首を捻挫しそうです。君子危うきに近寄らず、でここはパスします。足元さえよければ、潮の香りや波の音の中の絶好の 散歩道なんですが・・・。 渡船待合所の隣りにある物産店では、相島の海産物の加工品などを販売しています。お好みの品があれば、帰りの船に乗る前に、お土産として買われてもいいと思います。 |
|||||
| 期日 | 9月13日(日) 雨天中止。 | ||||
| 集合 | |||||
|
直方国土交通省下河川敷駐車場 7:30am(厳守) 渡船の出航時刻の制約があります。上記時刻には出発できるように、早めに集合してください。遅れたら自力で来てもらいますよ。 |
|||||
| 行程 | |||||
|
河川敷駐車場 7:30 → 相島渡船待合所 9:00 → 出航 9:20 → 相島到着 9:50 → 島内周遊 10:00〜12:00 →(昼食 〜13:30) → 相島渡船待合所 13:30 → 出航 13:50 → 新宮到着 14:10 → 直方15:30 |
|||||
| 参加費 | |||||
|
1500円(渡船料を含む。昼食代は含みません) 昼食は現地食堂特製の刺身弁当を用意します。価格 1200円。 自分で弁当を持参される方は、参加申し込みのときに教えてください。 おみやげとして、お持ち帰り用のさざえ飯も予約可能です。(1パック 350円) こちらも参加申し込みのときに教えてください。 昼食はどこか日陰を選んでしたいと思います。 |
|||||
| 参加締切 | |||||
| 9月 7日(月) | |||||
|
会員の皆さんから担当役員に連絡をお願いします。 当日までに連絡のない方は不参加とみなし、こちらから確認はしません。 |
|||||
| 持ってくるものなど | |||||
|
飲み物、昼食時に座るシート。 今月は山登りでなくウォーキングです。涼しくて軽快な服装で参加してください。暑さや日差しへの対策も忘れずに。 靴も履きなれたスニーカーなどがいいでしょう。 当日の空模様にもよりますが、雨具の準備もしてください。 障害者の方は障害者手帳を持参してください。 |
|||||
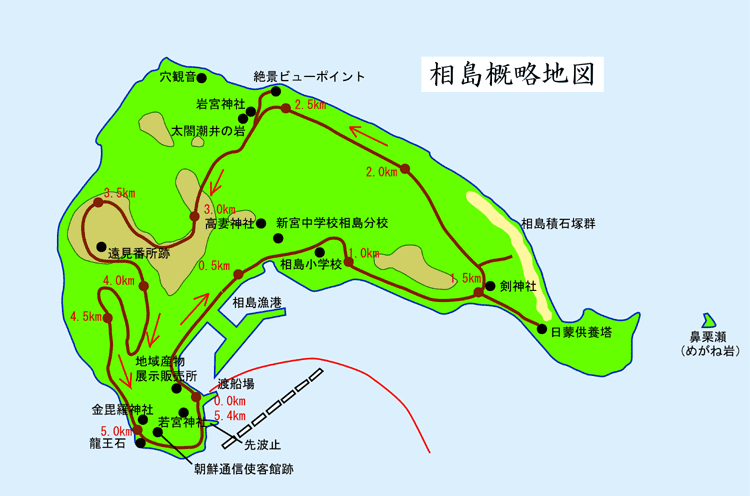 |
| 鼻栗瀬 (めがね岩) |
島の東300mの海上にそそりたち、全体が玄武岩で出来ています。 高さ20m周囲100mの海蝕洞があり、絶好の釣り場となっています。平成18年2月、鼻面半島とともに県指定文化財(名勝)に指定されました。 |
 |
| 日蒙供養塔 | 1274年(文永の役)・1281年(弘安の役)の二度にわたる元寇の時に相島で戦いがあったかどうかは分かりません。しかし百合越の海岸には 敵味方の遺体が数多く流れ着いたといわれています。島の人たちは塚を造って、その遺体を供養したそうです。現在の供養塔は昭和42年(1967)に 建立されました。 |
 |
| 相島積石塚群 |
島の北東、長井浜に古墳時代中期から後期にかけての古墳「積石塚」があります。一般には土を盛って作るのに対し、積石塚は石を積んだ古墳であり、
その数は254基を数えます。 平成13年、国指定史跡となりました。 |
 |
| ビューポイント | 島の北側で、穴観音への入口付近は、海と岩肌に植生する植物とが織り成す絶景です。 |
 |
| 太閤潮井の石 | 国内を統一した豊臣秀吉は、文禄元年(1592)・慶長2年(1597)に朝鮮へ出兵しました。諸国の軍勢が海路名護屋城に向かう途中、相島に立ち寄り 海岸の石を一個ずつ持って千手観音に航海安全と戦勝の祈願をしました。その積み上げられた石の山を、太閤潮井の石と呼んでいます。 |
 |
| 遠見番所跡 |
江戸時代に福岡藩は、玄界灘を眺望できる西端のこの地に遠見番所を設置し、毎日沖を見張りました。異国船が見えたらまず福岡に知らせ、
逃亡しようとした船は追跡して長崎奉行に引き渡しました。今は当時を偲ぶ石垣が残っています。 昭和51年に灯台が建設され、沖行く船の安全を見守っています。 |
 |
| 龍王石 |
「筑前国風土記付録」に「八大龍王石神、タカイシワラ(地名)と出ています。これが漁を生業とする海の男の信仰を一身に集める龍王石です。 ご神体は島の西海岸にある自然石で、周囲が750cm、横256cm、高さ216cmの石です。 |
 |
| 朝鮮通信使 客館跡 |
朝鮮通信使一行約300〜500人を接待した客館跡地です。平成6年度の発掘調査の結果、江戸時代の大規模な建物跡が見つかり、この場所に客館跡が あったことが判明しました。 |
 |
| 先波止 | 朝鮮通信使を迎えるため、福岡藩が天正2年(1682年)構築したもので、島民が延べ2ヶ月かけて先波止と前波止の二つを作りました。現在、前波止は 町営渡船の波止場で、対馬藩士や随行者が上陸しました。先波止からは通信使の一行が上陸しました。 |
 |
| このページの先頭へ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
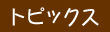 |